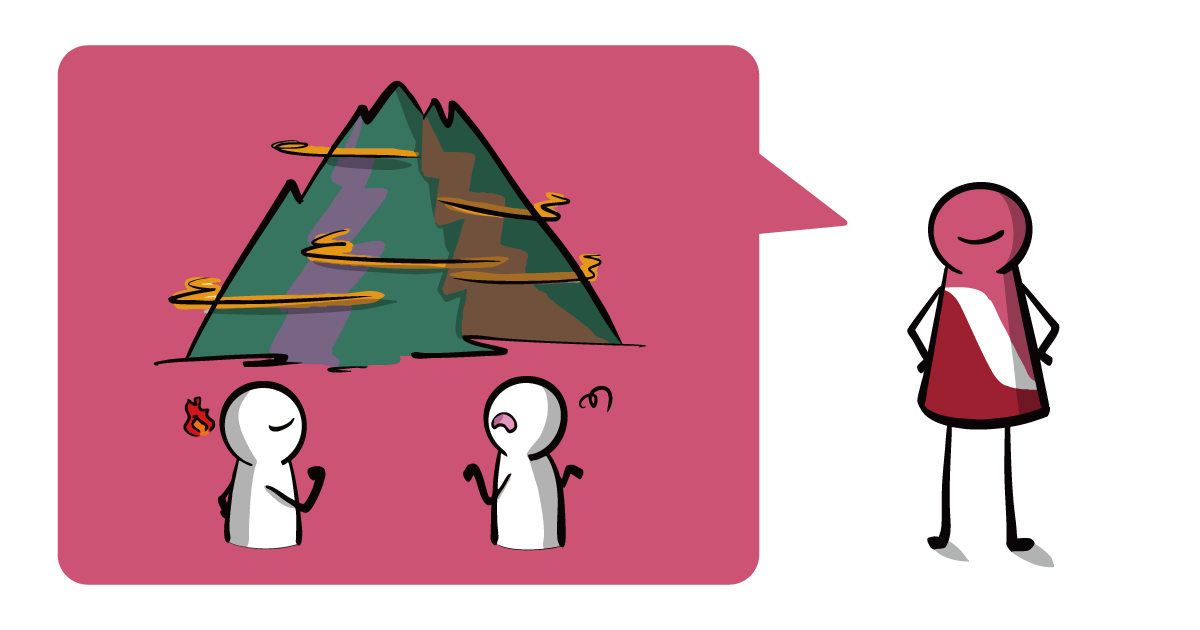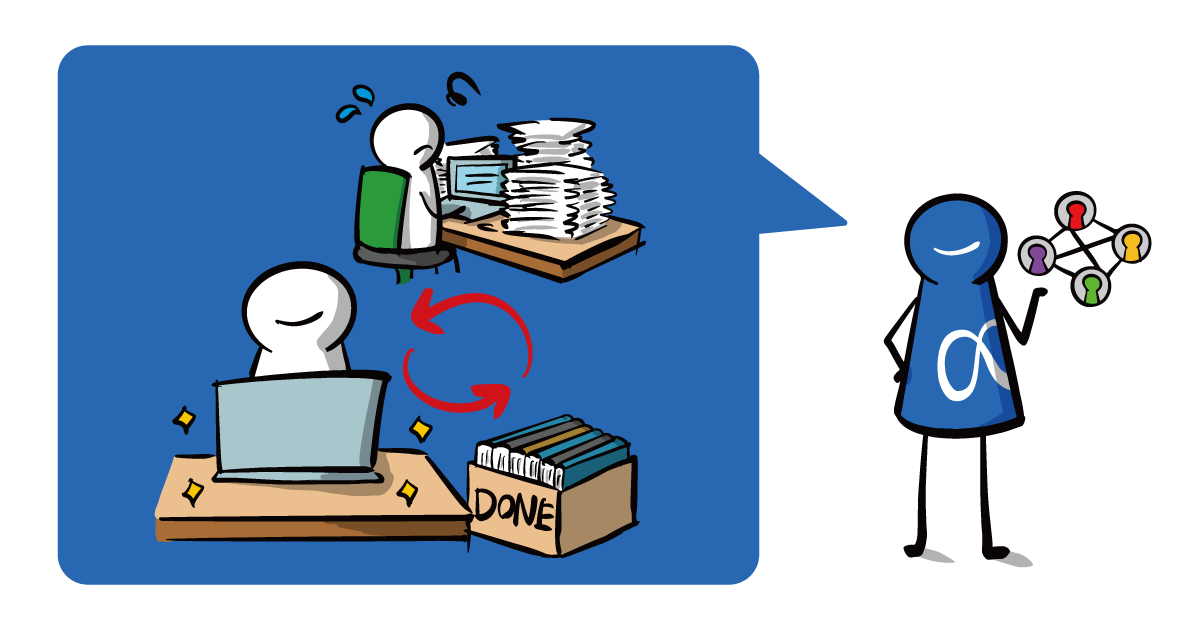会社設立にかかる費用|節約のポイントと実例
2025.09.03
![]() 読了時間目安
読了時間目安
4分
会社設立は、多くの起業家や個人事業主にとって新たなチャレンジの第一歩です。しかし、「会社設立の費用はどれくらいかかるもの?」「節約できる部分はあるの?」といった疑問や不安を抱える方も少なくありません。この記事では、会社設立時に必要な費用の内訳から、実際に節約するための具体的なポイント、さらに実例までを詳しく解説します。無理なく賢くスタートを切るために、ぜひ参考にしてください。
会社設立時にかかる主な費用

会社設立の際には、どのような費用が、どれくらいかかるのでしょうか。主な費用をご紹介します。
株式会社を設立する場合の費用内訳
会社設立時には、法定費用や手続きに伴う実費、場合によっては専門家への報酬など、さまざまなコストが発生します。まずは、株式会社を設立する場合の主な費用項目と目安を整理しましょう。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 15万円以上 | 資本金×0.7%、最低15万円 |
| 定款認証手数料 | 約5万円 | 公証役場で支払い |
| 定款の謄本交付料 | 約2,000円 | 定款の枚数で変動 |
| 収入印紙代 | 4万円 | 電子定款の場合は不要 |
| 専門家報酬 | 5~10万円 | 依頼する場合のみ |
| その他(印鑑等) | 1~2万円 | 実印・銀行印など |
合計:約24~30万円(自分で手続きした場合は20万円台前半も可能)
合同会社(LLC)の場合
株式会社よりも設立費用が抑えられる合同会社(LLC)も選択肢の一つです。
| 費用項目 | 金額の目安・備考 |
|---|---|
| 登録免許税 | 6万円(資本金×0.7%、最低6万円) |
| 定款認証手数料 | 不要 |
| 収入印紙代 | 電子定款なら不要 |
合計:約6~12万円
設立形態によって初期費用に大きな差が出るため、事業規模や将来の展望に合わせて選択しましょう。
会社設立費用を節約するポイント

会社設立時のコストは、工夫次第で大きく節約できます。ここでは、具体的な節約ポイントを詳しく紹介します。
電子定款を活用する
紙の定款を作成すると4万円の収入印紙代が必要ですが、電子定款であればこの費用が不要になります。自分で電子定款を作成したり、専門家や設立サービスを利用することで、初期コストを抑えることが可能です。電子定款の作成には多少ITスキルが必要ですが、設立代行サービスを利用すれば、手間をかけずに節約できます。
合同会社(LLC)の選択
合同会社は株式会社に比べて設立費用が安価で、定款認証も不要です。小規模なビジネスや、コストを重視する方には特におすすめです。法人格としての信用や運営の柔軟性も高く、近年選択する起業家が増えています。
専門家への依頼範囲を絞る
設立手続きをすべて専門家に依頼すると報酬がかさみますが、定款作成や登記申請など「必要な部分だけ」依頼すればコストダウンが可能です。例えば、電子定款の作成のみを専門家に依頼して、その他の手続きは自分で行うことで、数万円単位で節約できます。
オフィス・備品の初期費用を抑える
会社設立時は、オフィスの賃貸や備品購入にかかる費用も無視できません。自宅やバーチャルオフィスを活用すれば、賃貸初期費用や備品購入費を大幅に削減できます。まずは必要最低限の設備からスタートし、事業の成長に合わせて拡充するのがポイントです。
資本金は1,000万円未満に設定
資本金1,000万円未満で設立すれば、設立から2年間は消費税の納税義務が免除されます。資本金を高く設定するメリットもありますが、税負担や資金繰りを考慮して適切な金額を選びましょう。
自分でできる作業は自社で対応
印鑑作成や書類取得、申請などは自分で行うことで外注費用を抑えられます。最近ではオンラインで印鑑作成や書類取得ができるサービスも増えており、手間を最小限にしつつコストカットが可能です。
節約実例・ケーススタディ
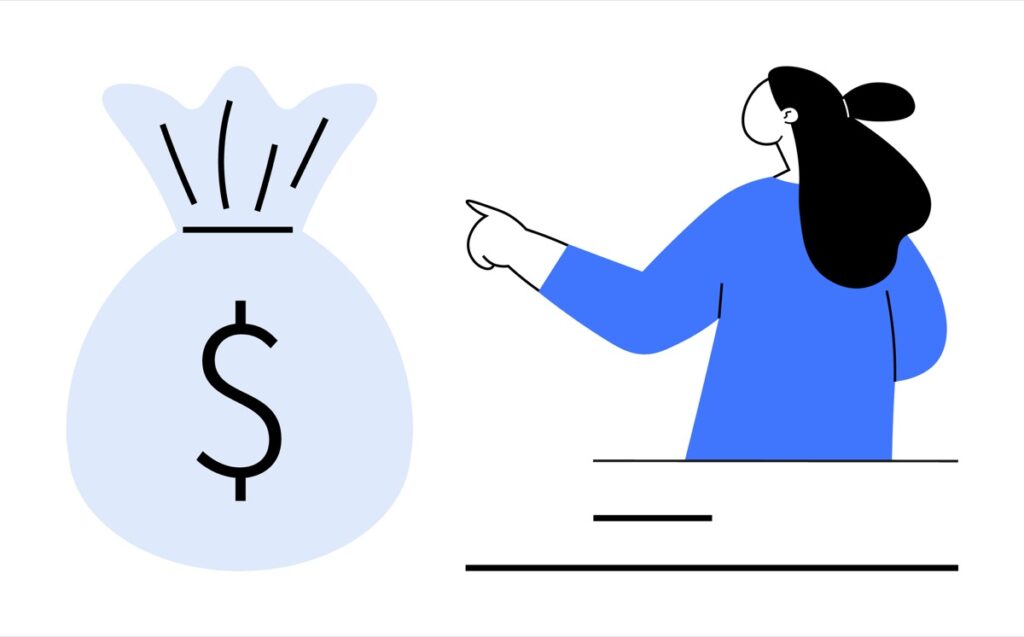
実際にどのように節約できるのか、具体的なケースをいくつかご紹介します。
ケース1:電子定款+自分で手続き
- 登録免許税:15万円
- 定款認証手数料:5万円
- 電子定款作成:自分で対応(印紙代0円)
- 印鑑作成・書類取得:約1万円
- 合計:約21万円
電子定款を自作し、手続きを自分で進めることで、設立費用を大きく削減できた事例です。多少の手間はかかりますが、コスト重視の方にはおすすめです。
ケース2:設立サービス利用+合同会社
- 登録免許税:6万円
- サービス利用料:1万円
- 印鑑作成・書類取得:約1万円
- 合計:約8万円
設立サービスを活用し、合同会社を選択したケースです。必要な部分だけ外部サービスを使い、最小限の初期費用で法人化を実現しています。
ケース3:専門家に一部のみ依頼
- 電子定款作成のみ専門家に依頼(報酬2万円)
- その他は自分で対応
- 合計:約23万円
専門家のノウハウを活かしつつ、コストを抑えたバランス型の事例です。自信がない部分だけプロに任せることで、安心と節約を両立しています。
※オフィスを借りず自宅で設立した場合。オフィス賃貸や設備投資を行う場合は別途費用が発生します。
※ご紹介したケースは参考例です。実際の設立費用や条件は、事業内容や地域、手続き方法などによって変動しますのでご注意ください。
その他の節約アイデア

創業支援制度や補助金・助成金の活用
各自治体や国の創業支援制度、補助金・助成金を活用すれば、実質的に設立費用の負担を軽減できます。事前に情報収集し、利用可能な制度は積極的に申し込みましょう。
会社名義で自宅兼事務所契約を行う
自宅を事務所として活用することで、家賃の一部を経費化できる場合があります。税務上の取り扱いも確認し、無理のない範囲で活用しましょう。
オンラインツールやテンプレートの活用
無料・低価格の会計ソフトや事務テンプレートを活用すれば、事務作業の効率化とコスト削減が同時に実現できます。
クラウドサービスの活用
バックオフィス業務や顧客管理、請求書発行などもクラウドサービスを利用することで、初期投資を抑えつつ業務効率を高められます。
会社設立で失敗しないための注意点

節約ばかりに目が行きがちですが、設立後の運営や信用面もふまえて判断することが大切です。資金計画の甘さや、許認可・名義変更の見落とし、定款・登記の不備、法人化後の事務負担増加など、設立時に陥りやすい落とし穴にも注意しましょう。
- 必要な許認可や契約・資産の名義変更リストを作成し、漏れなく対応する
- 定款や登記書類は専門家にダブルチェックしてもらう
- クラウド会計やアウトソーシングを活用し、事務負担を軽減する
- 設立後も、定期的に運営を見直して改善を続ける
まとめ

会社設立時の費用は、工夫次第で大きく節約できます。電子定款の活用や合同会社の選択、専門家への依頼範囲の見直し、オフィスコストの最適化など、自分に合った方法を選びましょう。実際の事例を参考に、無理のない範囲でコストを抑え、設立後の運転資金に余裕を持たせることが大切です。
まずは費用の内訳をしっかり把握し、節約ポイントを押さえて賢く会社設立を進めてください。設立後の事業運営に集中できるよう、スタート段階でコストを最適化することがポイントです。会社設立の第一歩を、賢く・堅実に踏み出しましょう。
この記事を読んだあなたに
おすすめの記事